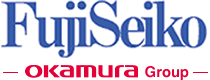
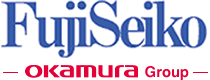

自社の強みと市場のニーズをマッチングさせ
新たな事業の柱を立てる!
2020年春に発売された「バゲッジキーパー」は、荷物預かり業務の省人化を実現する自動搬送型荷物保管システムです。
当社の強みである全自動貸金庫システムの技術を応用し、新たな価値を世に送り出した2人の設計担当者に、
製品の開発ストーリーと、設計の仕事の醍醐味について聞きました。


樟:私は自社製基盤のプログラムやPCアプリケーションなどのソフトウェアの設計を担当しています。
小野:ソフトウェアは人間に例えれば「頭脳」にあたります。これに対して私たちメカニカルの設計者は頭脳が出す指令通りに動く「ボディ」を設計します。樟:逆にこんなボディだから、こうすればボディに適した動きになる、ということも考えます。
小野:当社は金庫室扉や貸金庫といった金融機関向けの製品で実績があり、メカトロ技術を取り入れ、貸金庫をユーザーの手元まで搬送する自動貸金庫システムも提案しています。この技術を活かして新しい分野に踏み込もうということで、ホテル業界向けに開発したのがバゲッジキーパーです。観光立国を目指す日本ですが観光業界は人手不足が深刻化しています。現場の困りごとを技術で解決しようと、開発プロジェクトがスタートしました。
樟:コンセプトの立ち上げから1年以内に展示会に出展し、次の年に1号機を受注しました。トータル1年半で製品化しましたから、かなりのスピード感で開発が進みましたね。


樟:貸金庫のユーザーは契約者に限られますが、バゲッジキーパーは外国人観光客を含め不特定多数の人が利用します。重い荷物を放り込んだり、詰め込こんだりといったラフな使い方をされた場合でも、動きを止めないしくみを実現することに苦労しましたね。
小野:使われ方を想像しながら開発するというのは初めての経験でした。仕様決めの基準もありませんし、誰かが正解を持っているわけでもありません。大変でしたが、自分たちでスタンダードを決めていけるというのは、手応えが大きかったですね。導入してもらえる機能と価格のバランスを強く意識したのもこれが初めてでした。どんどんと機能をつけていくと当然コストは上がります。技術ありきで開発するのではなく、価格を含めお客様が何を望んでいるかを最優先させたのは、新鮮な体験でした。
樟:コストを抑えるという点では、部品を増やさずにすむようソフト的なコントロールを実現することがキモになりましたね。たとえば1号機では、預かった荷物を搬送してラックに格納する際、人が手で持ってそっとおくような動きを実現して、静かなホテルでも搬送音が響かないようにしました。
小野:まず市場に投入し、導入していただいたお客様の意見を聞きながら、スピード感を持ってバージョンアップしていこうという考え方の製品なので、今後の成長が楽しみです。
樟:従来の金融機関向けの製品は、セキュリティ的に閉じた空間での仕事でした。クラウドに繋がったオープンな環境でのシステム設計でも経験を積んでいきたいですね。
小野:きちっとしたルールと伝統がある金融機関向けの設計がある一方で、バゲッジキーパーのように自由な開発もある。仕事の幅が広がって面白いですね。



樟:技術部には、メカ設計、システム設計に加え、電気設計を担当する部署もあります。「ボディ」「頭脳」「神経」が揃っているというわけです。それぞれの目線でこうしたい、という意見があるので、開発においてはぶつかることもあります。
小野:自分の意見を言わずに黙って進めるより、意見をぶつけあった方がいいものができると皆が信じているから。
樟:そうそう。意見をすり合わせる中で、お互いを活かす新しいアイデアが生まれることもありますね。
小野:技術部として、上からやれと言われてやるのではなく、社員一人ひとりが持っていることを発信しよう、ということを大切にしているんですよね。これは事業の新しい柱を立てようというときに特に大事なことだと思います。
樟:自分の意見を言いやすい、アイデアを実現しやすいというのは、自社で設計から製造までやっているからこそ。「ここを少しカスタマイズしたい」というときも、外部に依頼するとなるとどうしてもワンステップ遅れてしまいます。そこを全部社内でできるのは強い。
小野:会社の方向性を踏まえた上での共通言語があるので、伝えたい本質がきちんと伝わります。製造部門とも、どうすれば品質が安定するか、同じ機能を持ちながらどうコストを落としていけるか、といった点を、踏み込んで、しかもスムーズに話し合えます。そこまで自社でできるのは、自分たちの強みであり、やりがいでもありますね。
樟:自分のアイデアをかたちにできる環境があるということが一番です。技術はどんどん進化していますから、そこは入社してからでいい。「今、何ができるか」じゃなくて、「これからどう身につけていくか」が大事です。
小野:メカ側でいうと、完成した製品を工場で確認できるというのが大きいです。自分の頭の中で考えていたものと現実にできたものを比べて、そこから学んで、次に活かすことができます。これを繰り返すことで、成長や実感が味わえます。
樟:工場だけでなくメンテナンスなどで現場に行く機会もあるので、実際に世の中で使われているところを見る喜びもありますね。

